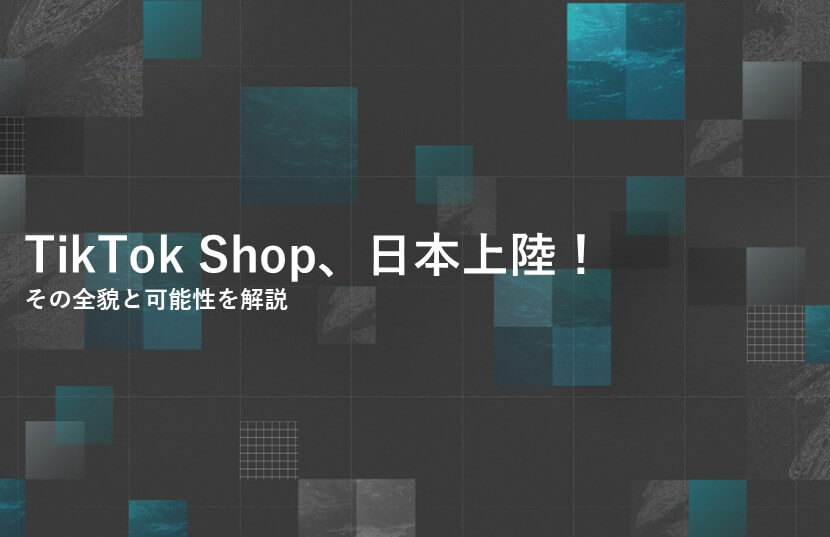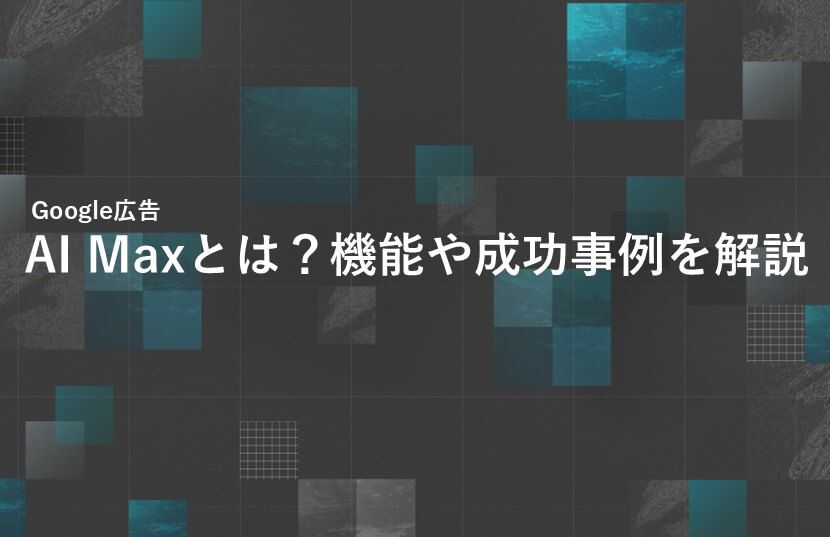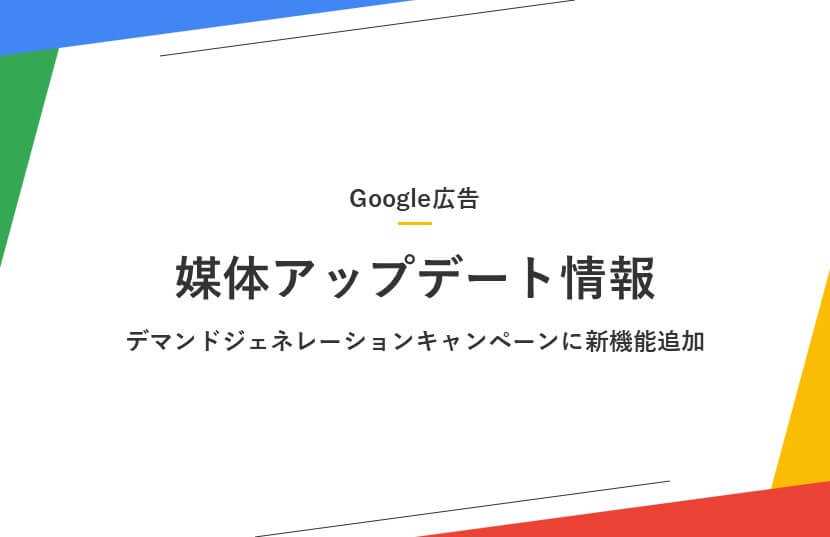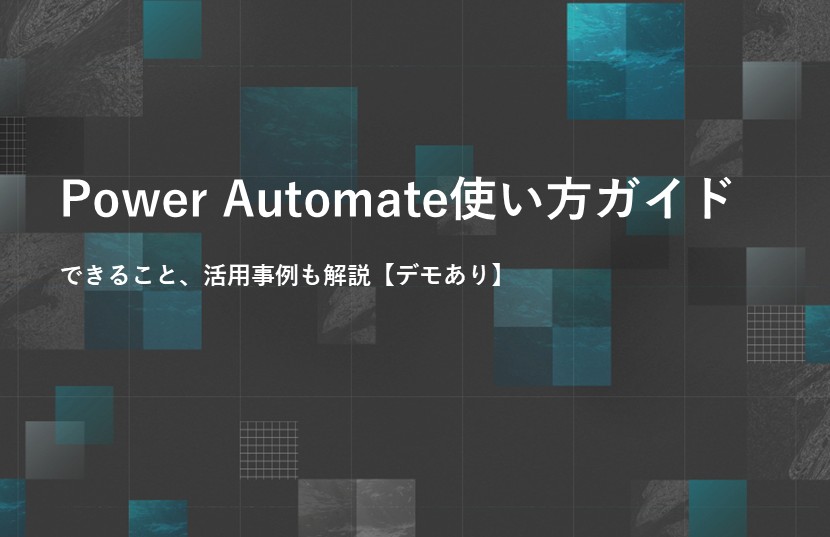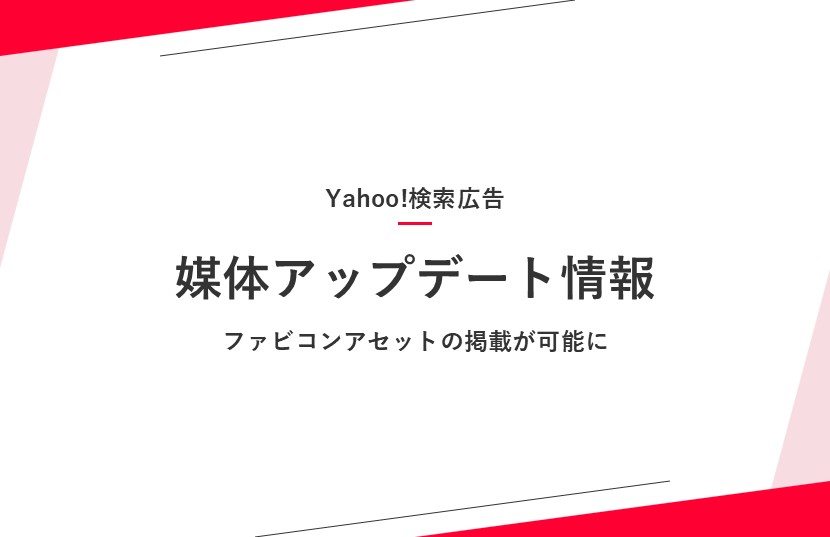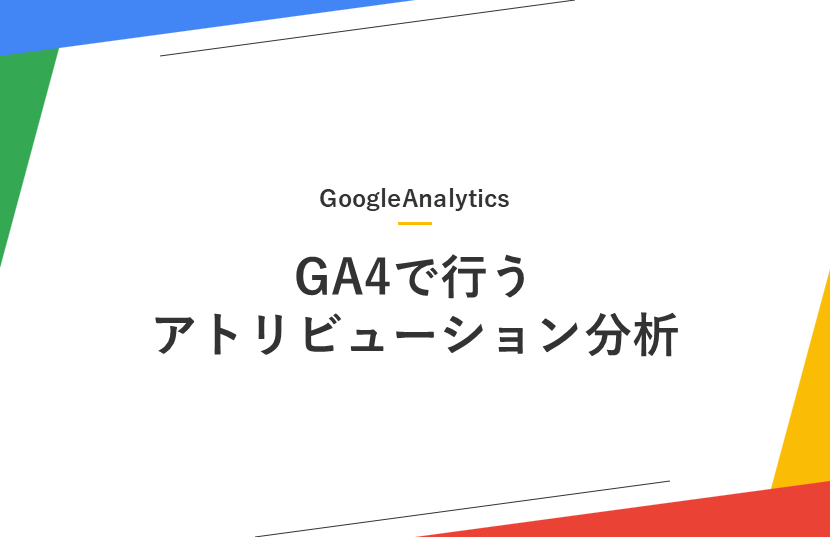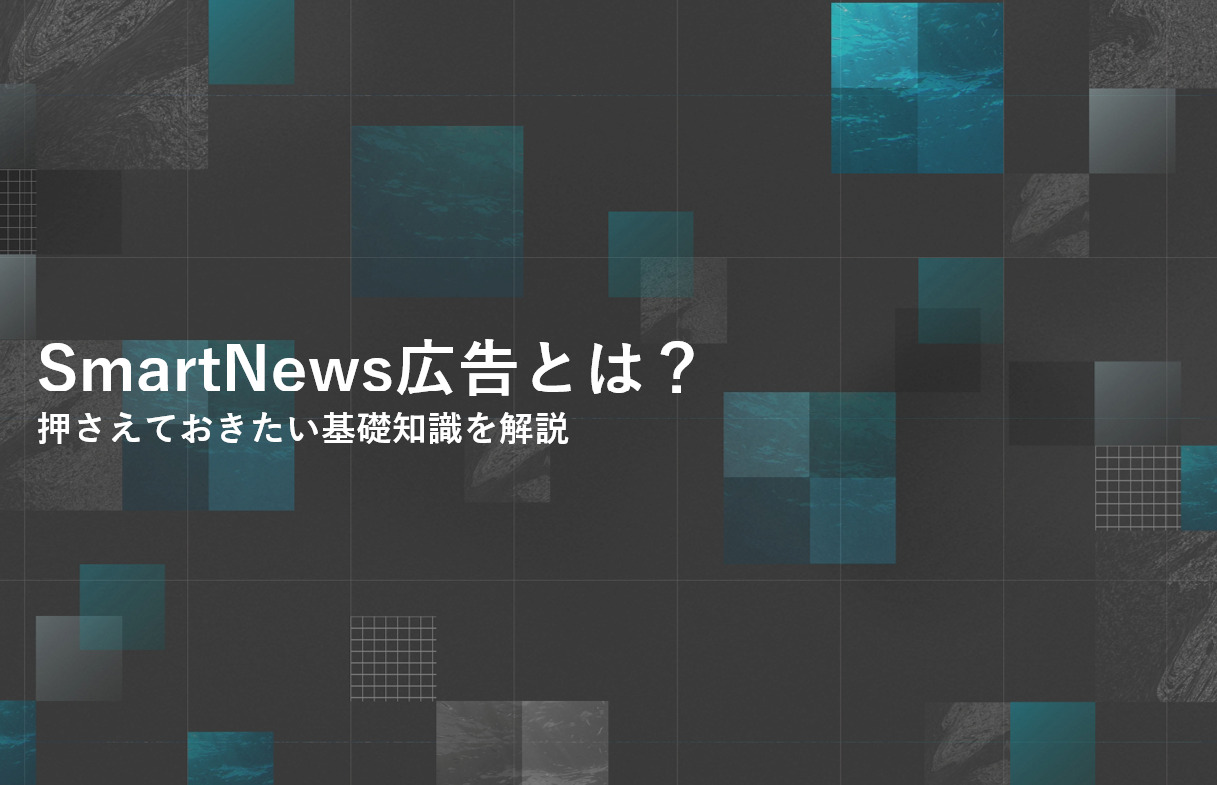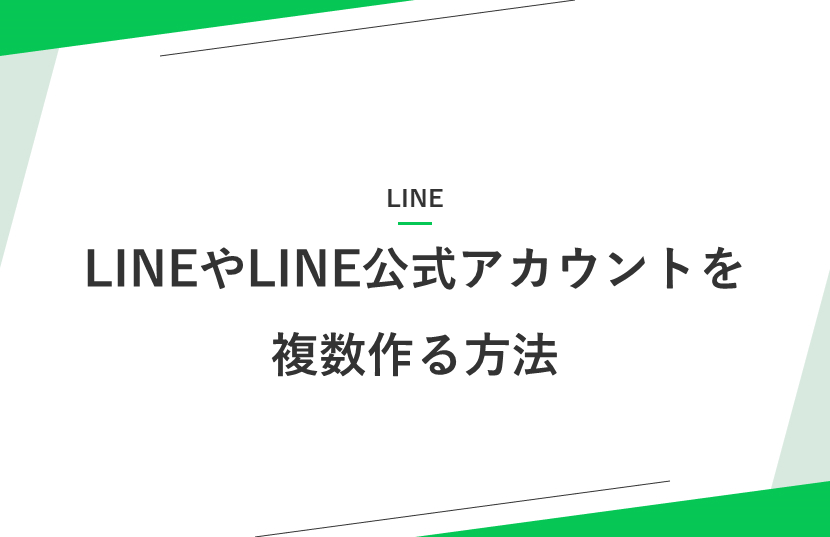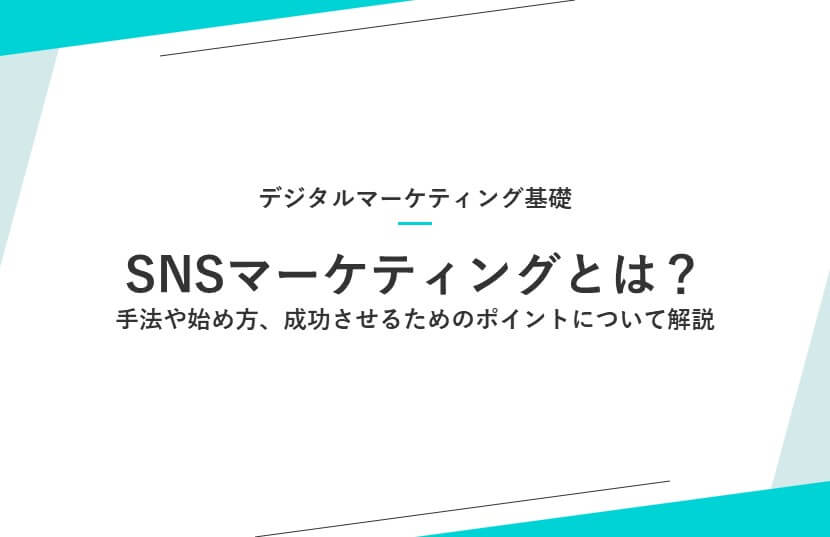-
TikTok Shopが日本でローンチ決定!開始時期、期待されるメリットを徹底解説。EC担当者、インフルエンサー必見。あなたのビジネスを加速させる最新情報をいち早くお届けします。
-
Google広告の最新機能「AI Max」について、広告運用担当者向けに、主要機能の詳細を丁寧に解説します。執筆は豊富な広告運用実績を持つデジマールが担当。
-
広告運用担当者向けに、Google広告のデマンドジェネレーションキャンペーンの最新アップデートを解説。GDN対応や配信チャネルの管理機能など、注目の変更点を網羅。
-
Power Automate初心者向けに、Power Automateでできることやメリットから使い方、活用事例まで丁寧に解説します。執筆は実際にPower Automateの活用実績があるデジマールが担当します。
-
2025年4月から、企業ロゴやブランドロゴ、またはサイトの内容を象徴する画像である「ファビコンアセット」を掲載することができるようになりました。入稿規定や設定方法を丁寧に解説いたします。
-
-
-
-
当記事では、LINEやLINE公式アカウントのアカウントを複数作成する方法から、メリット、注意点、事例まで解説します。複数のアカウントを活用したい方は必見です。
-
SNSマーケティングの手法や各SNSの特徴、SNSマーケティングを成功させるためのポイントなどを丁寧に解説していきます。