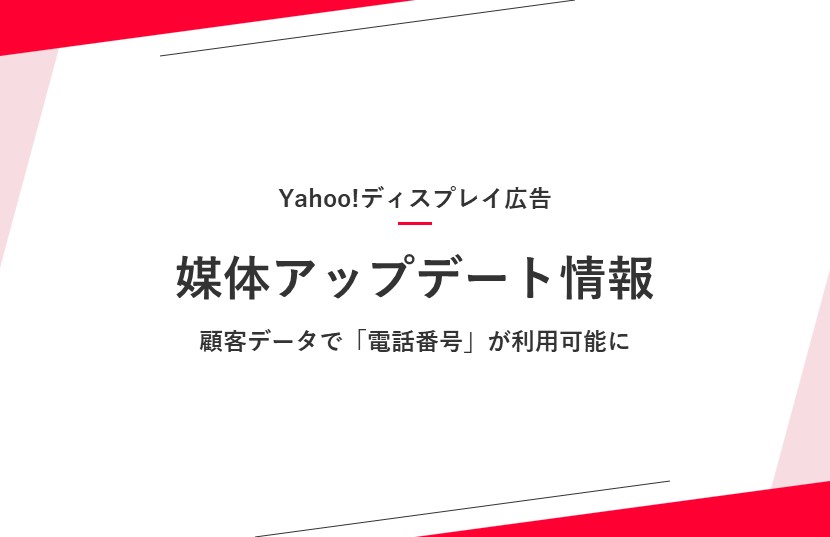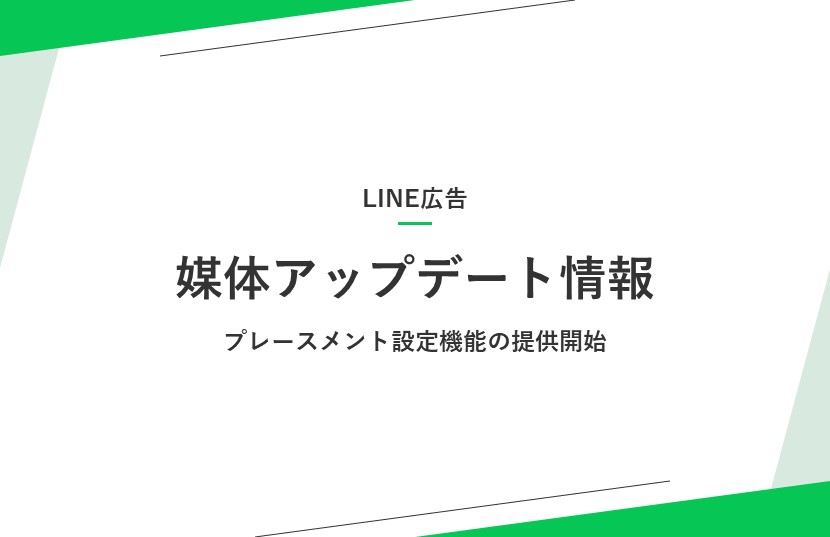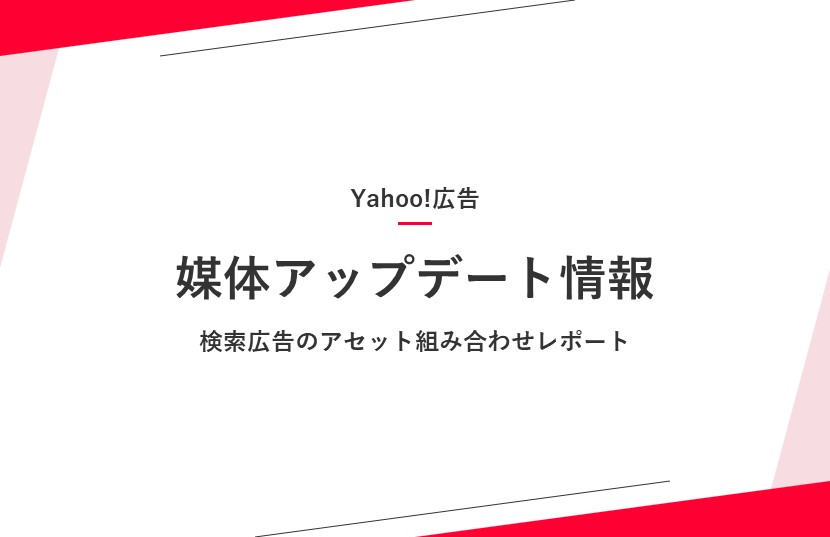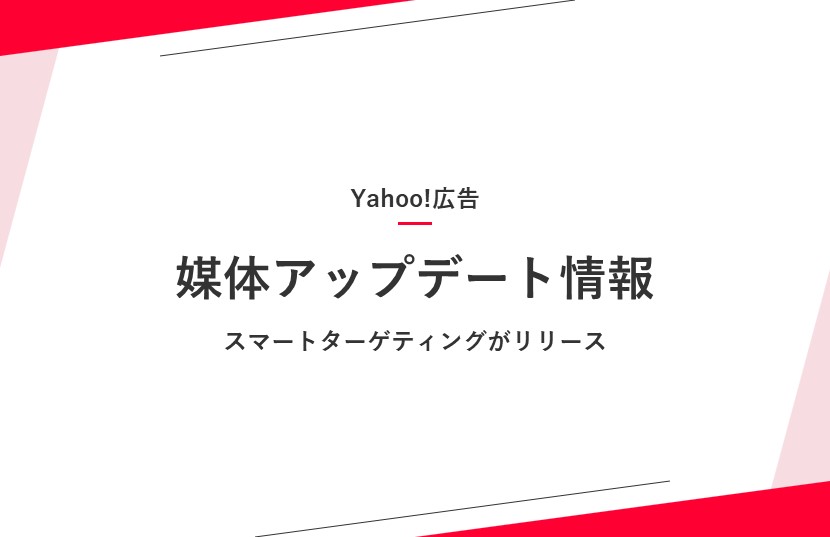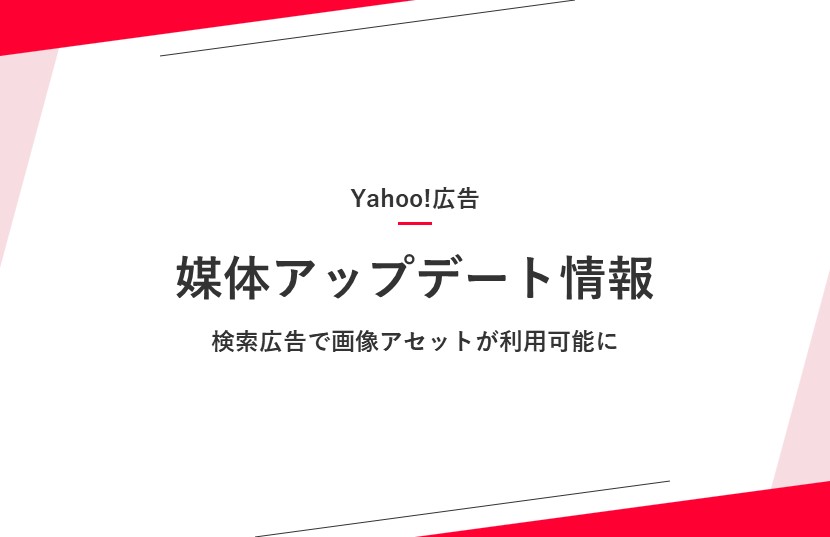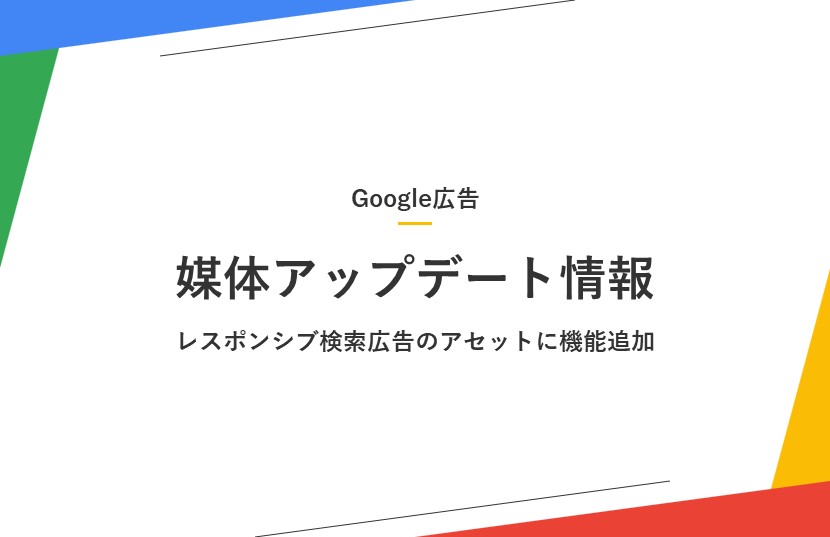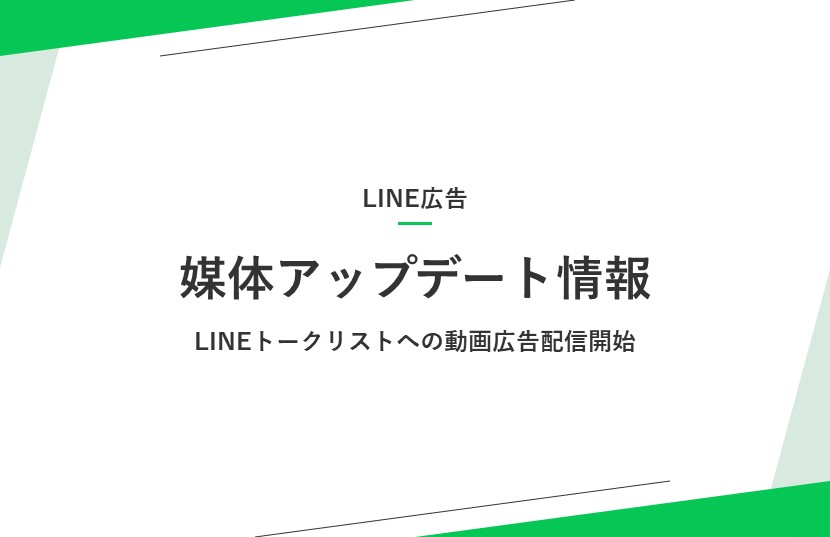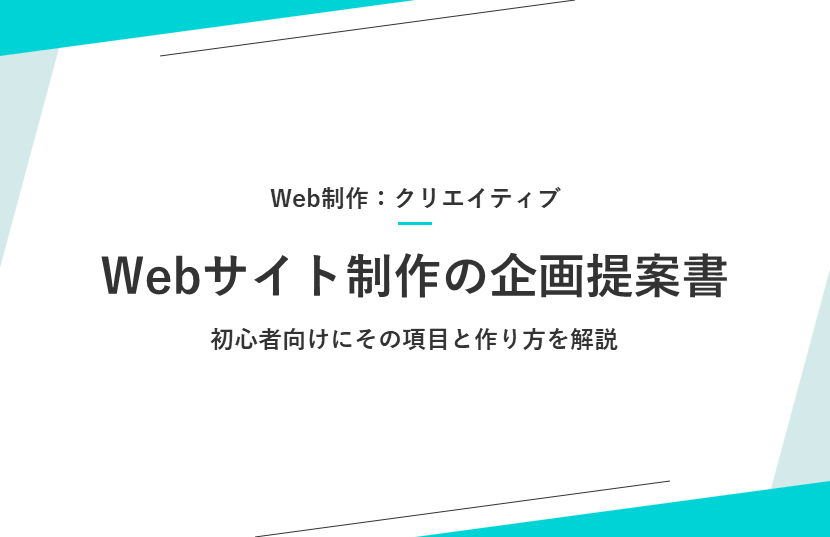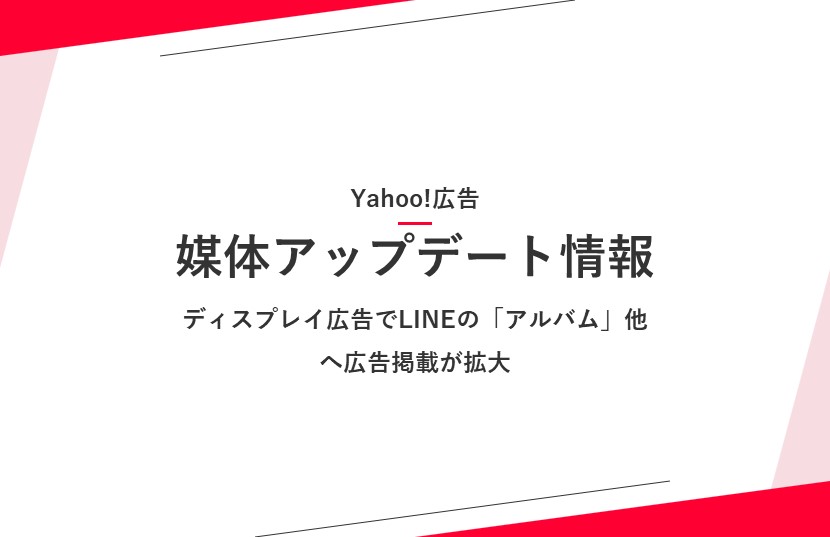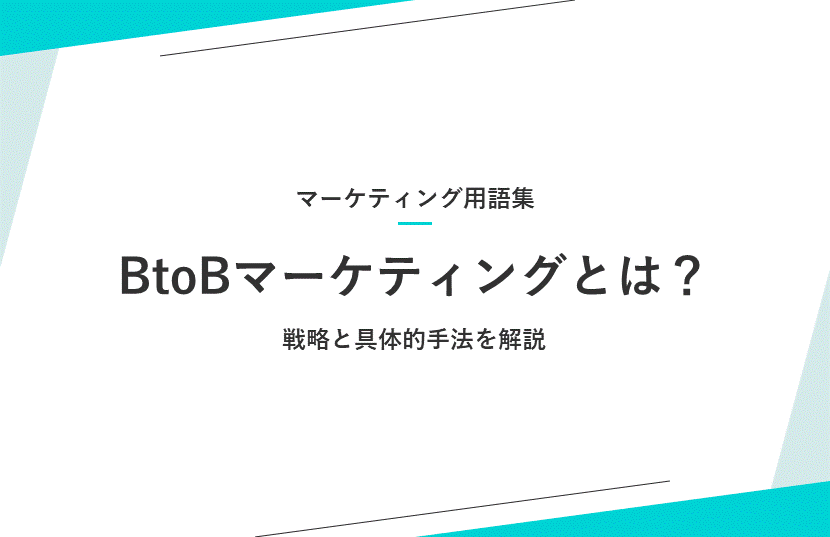-
Yahoo!ディスプレイ広告で、オーディエンスリストの「顧客データ」にて、メールアドレスだけではなく電話番号による顧客データのアップロードが可能となりました。
-
LINE広告で、プレースメントを選択して広告を配信できる機能が追加されました。
-
2024年3月6日より、Yahoo!検索広告にてアセット組み合わせレポートを利用できるようになりました。
-
2024年2月28日に、Yahoo!ディスプレイ広告にて、「スマートターゲティング」機能がリリースされました。
-
2024年4月からYahoo!検索広告にて、画像アセットが利用できるようになります。
-
2024年2月1日のGoogle広告アップデート情報です。レスポンシブ検索広告のアセットに、複数の機能が追加されています。
-
2024年2月より、LINE広告のトークリストに動画広告が掲載できるようになりました。
-
初心者の方でも理解しやすいように、Webサイトの企画提案書の作成方法を丁寧に解説していきます。
-
2024年1月24日のYahoo!ディスプレイ広告(運用型)のアップデート情報です。
-
BtoBマーケティングの全体像と重要な考え方を理解し、適切な戦略を立てることが重要です。